片手取り外巡り相半身外入り身転換呼吸法






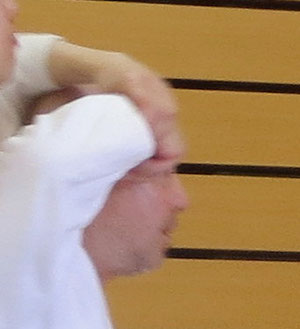


交差取り下段受け流し入り身の魂氣と魄氣

②受けの相半身交差取りに母指先の反り方向へ内巡り

③右半身魄氣の陰のまま右足先と共に魂氣を剣線の左方(受けの外側)に外す

④呼吸法で降氣の形へ

⑥吸気で右半身魄氣の陽にて呼吸法陽の陰の返し突き近似
右母趾先は剣線に向け受けの真中に、魂氣は真中を避けて受けの左側頸に進める
単独動作は「単独基本動作1」「館長」の“下段受け流し”参照

⑦後方の左足を送り足で右相半身外入り身、魂氣は陽の陰から陰の陰へ母指先の反りと前腕伸側を受けの側頸と背に着け、受けの腰に巡って取りの丹田に結ぶと、陰の陰の入り身運動であり残心の姿勢に一致。入り身投げが成り立ち受けは取りの左足後方に螺旋で落ちる。
片手取り外転換で陽の陽2本
1. 片手取り外転換鏡返し

①左半身陰の陽で魂氣を与える・受けは逆半身で取ろうとする


②左半身陰の魄氣で左足先を外に置き換え軸足として外転換へ・取らせた魂氣は陽の陽で眼前に・右手は転換と共に陰の陽のまま丹田に巡る


③右手で下から手首を受けて取り・左手を陽の陰に巡って外し・杖返し突き近似で陰の陽に巡って受けの手背に被せようとする 魄氣は右足先も置き換えて転換しており陰である

④右足から踏み替えて左半身陰の魄氣に入り身転換・左手を陰の陽で丹田に結ぶと同時に左足を右軸足の踵の後ろに置き換えて右半身残心で受けは取りの後方へ螺旋で落ちる。
入り身転換のところを後ろ回転であれば受けはさらに半回転増して落ちる。その点では四方投げである。
2. 下段に与え陽の陽で外転換にて取らさず丹田に巡り小手を取り返す

①左半身陰の魄氣で魂氣を与えようとする

②受けは逆半身で片手にて取ろうとする・取りの左足は外に置き換え外転換で右半身・左魂氣を取らさず陽の陽に広げて眼前に置く。右手は後ろから丹田に陰の陽のままで巡る。

③左手を陰の陽に巡ると丹田に降りて受けの小手に当たり結べば取る・その時右足腰を後方に一歩置き換えて丹田の右手は同時に後方へ陰の陽で巡らしており・左半身陰の魄氣。
*小手に当たらなければそれに結ぶことはない。つまり小手を取ることはない。丹田に結んで昇氣に巡り側頸から呼吸法。そこで受けとの密着感がなければ両手で気の巡りにて右魂氣を陽の陰で受けの左側頸へ返し突きで右半身入り身投げ

④左足先を更に左外方に置き換え陰の魄氣で転換と共に左手を降氣の形に巡らせると・右手を腰の後ろから返し突き近似にて陽の陰で受けの手背にかぶせる。左足を右踵の後ろに置き換えると右手は陰の陽で丹田に結び右半身残心・受けは取りの背面に螺旋で落ちる。
片手取り四方投げ表(二教の手)

①左半身にて魂氣を陰の陽で下段に与えて逆半身片手取り・陰の魄氣から左足先を外に置き換え・魂氣を陽の陽で中段に示す


②置き換えた左足を外転換の軸足とし、同時に降氣の形から回外して脇を開くと二教の手。受けの手は反屈となり・取りは右手で四方投げの持ち方。右足を寄せて右半身陰の魄氣へ。

③右半身陰の魄氣で外転換の後、四方投げの持ち方をしている右手の手背を額に結ぼうとしている。二教の手の左魂氣は与えた接触から一息で額に結ぶ。受けの左手は腰の後ろから常に陽で発し得る。

④陰の魄氣からさらに右足先を前方回転の軸足とすることで右手背が額に結ぶ。取りと受けの魂氣が共に額へ氣結びすることで前方回転の軸足が安定する。
それによって初めて四方投げの持ち方が確立し、以後の前方回転が可能となる。
目付けを下に落とさない。 ②〜④の下段から上段の二教の手(降氣の形から回外しながら脇を開く)は一気に動作し、受けの手を反屈に導くと共に回転の軸足形成は腰を落とし体軸が垂直のまま地に降りることで取りの手背は額まで相対的に上昇し死角に入る。

⑤右足を軸として後方の左足を前方回転して右足先の前を通る。

⑤’左足の膝を曲げて足先を軸足の側に戻す 左手は陰で腰に。

⑥左足が軸となり捻られている右足は受けに向かって足先が半回転して右手が同時にその方向に正面打ち近似で伸展する

⑦右足を180度置き換えた瞬間前方回転は成立し同時に右手は額から受けの項に正面打ち近似で伸展して結ぶと、受けの魂氣も自身の項に結ぶ。 取りの左手は陰・右手は陽
受けの視野に入らない

⑧右手を臍下丹田に巡り右半身入り身運動で左足は送り足にて残心・受けは取りの丹田を経て左足後方に落ちる
二教の手から四方投げの持ち方




片手取り二教の手で入り身転換

①左半身で与える

②受けは逆半身で片手取り

③降氣の形で回外しながら脇を開いて入り身転換 取りの魂氣は二教の手に受けの手は反屈に

④二教の手と受けの反屈した手首の間に右魂氣を陽の陽で差し入れて手背をすくう 入り身転換で右半身の右足先と右母指先を揃える

⑤二教の手がはずれて陰の陰で丹田に巡り更に外巡りで陽の陰へ 右手は受けの手を下から把持

⑥左手は陽の陰で受けの項に当たると陰の陽で側頸に結ぶ
下段に与え外転換外巡りで取らさず対側で下段受け流し入り身転換

①左半身で左魂氣を与えると受けは逆半身で取ろうとする

②左手を陰の陰の外巡りで外して左足先も剣線の外に置き替え 右手は陽の陽

③右手も陰の陰で下段受け流し 左手は陰の陰の外巡り

④右半身へ転換すると右足先は剣線から外れて陰の魄氣
右足をその場で踏み込み軸として左手は脇を閉めてから陽の陽で横面打ち入り身へ(坐技呼吸法近似)左足先は逆半身外入り身へ(外して詰める)

⑤逆半身入り身転換で右半身 左足が軸となる陰の魄氣で同側の魂氣は横面打ち入り身転換で受けの側頸に陰の陽で結ぶ
横面打ち相半身内入り身・受け流しから外入り身転換

①左相半身で対峙

②受けは右逆半身で横面打ちに。取りは左手の降氣の形にて上段に受けるが、後手であるから左手足は入り身に進めることができない。左足を軸として右相半身で振込突きへ。(相打ちの場合、降氣の形から陽の陽の結びで逆半身一教運動表)


④振込突きで相半身となっている。受けは外から左手で突きを払う。取りの左手は陰の陽で丹田に巡って横面打ちを受け流す。


⑥払わせた右手は陰の陽で丹田に巡り、止まらず右足を軸として右手は外巡りで受けの右手を上から払い

⑦左手を腰の後ろから横面打ち(または返し突き)で左半身外入り身転換で右半身陰の魄氣。右手足先を揃え左手は陽の陽(または陽の陰)から陰の陽で受けの側頸に結ぶ
横面打ち外転換

①左手を陰の陽の降氣の形で受けて左足を入り身に進めず、逆半身から外に置き換えて外転換へ

②左手は陰の陰で丹田に巡ると共に、右手を陰の陽の上段から氣の巡りで受けの右手の遠位に当てる

③外転換で右半身陰の魄氣となり剣線が外れる。右魂氣は陽の陽で受けの右手に結んでいる。ここから左半身外入り身、または右手を陰に巡って受けの右手首を取る、あるいはそれを丹田で左手に持ち替えて受けの左手の動作に対して先手で中心を取るなど。
陰の陽で与えて正面打ちにあたる


横面打ちに陰の陽で受け流し
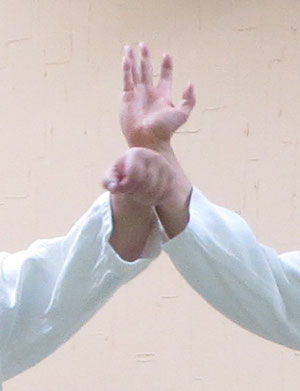


坐技胸取り相半身入り身運動

①正座

②右半身入り身運動に対して受けは逆半身で胸取り

③相半身で振込突き入り身運動に受けは外から払う

④陰の陽で丹田に降りて降氣であたれば尚も陰で巡り丹田に結ぶ
坐技胸取り逆半身横面打ち入り身運動・昇氣で呼吸法

①左半身に受けが逆半身で胸取りに来ると同時に、吸気で逆半身横面打ち入り身運動

②呼気で降りると受けの上肢にあたり、魂氣は陰の陽でさらに降りる。降氣であたれば尚も陰で巡る

③丹田から巡って昇氣で側頸に結ぶと母指先は耳の後ろに位置する。ここまで呼気。

④吸気で魂氣を陽の陽にして母指先から反りの方向へ発すると、前腕の撓骨側が受けの側頸に接して受けの体軸を魂氣が降りる。
後ろ肩取り入身転換反復による氣結び

①取りの左肩に受けの手が当たる

②右足を軸とする踏み替えにて左半身陰の魄氣で上段に与える。逆半身となっている。

③受けの手刀に当たり抑えを受けて陽の陰で巡り、左足先を軸足に踏み替え目付から転換へ(この画像のみ背景は不一致)

④右半身の陰の魄氣に入身転換と同時に左魂氣は陰の陰で丹田に巡る

⑤取りは右半身陰の魄氣で左手が受けの左手と共に丹田に結んだ。右足先を後方に置き換えると丹田への結びを保ったまま左半身の体の変更となり、単独動作陰の陰の入身運動に一致。後ろ取りの体の変更は受けとの間合いが技を生む連なりに適している。例えば四方投げ。片手取りからは隅落とし裏。体の変更を陽の陽で差し出すと、受けは取りから放たれ結びは解消する。

⑤左半身陰の魄氣の場合
後ろ両肩取りの氣結び


上段に与えて四方投げ表

①陰の陽で上段に与え受けは手刀で守り相半身となる あたれば陽の陽で半歩内入り身が手順

②ここでは陰の陽で丹田に巡りつつ外巡りで陽の陰にて正面当てとし・左の魂氣を陰の陽で手刀の下から当て・陽の陽から陰の陽に巡って丹田に結ぼうとする。魄氣は陰のまま。

③正面当ては魄氣の陽で相半身入身とし、右足を軸として踏み・受けに払わせた右の魂氣を丹田に陰の陽で巡りながら左足を後ろに置き換え内転換とする。受けの後方の足先に取りの右足がある。

④魄氣は右半身の陰となり右足先は受けの左足の前にあって前方回転の軸足とする(右外側に外股として腰をそこに落とす)右手は四方投げの持ち方で振りかぶる。四方投げ表へ。

⑤右足を外側に外股として腰をそこに落とすと前方回転の軸足。右手は四方投げの持ち方で振りかぶる。ここでは体軸も迎えに行っている。前方回転の始まり。
片手取り外巡り二教









 *神氣館【 高槻市 天神町道場 】 Shinkikan aikido tenjinmachi-dojo
(公財)合気会公認道場 Takatsuki-city Osaka JAPAN
大阪府合気道連盟加盟道場
開祖植芝盛平の言葉と思いを動作する basic techniques from words and thoughts of the Founder, Morihei Ueshiba
不動の軸足に陰の魂氣:〝吾勝〟 非軸足と魂の比礼振り:〝正勝〟
〝この左、右の気結びがはじめ成就すれば、後は自由自在に出来るようになる〟:軸足交代
二つはこんで一と足すすむ・入り身一足と、体軸に与る両手の巡り:〝左右一つに勝速日、業の実を生む〟
〝正勝吾勝〟で剣素振り 合気の剣は〝勝速日〟
「天の浮橋」のタイトルに 3. 合気道は争わない、表と裏で気結びする 2024/5/20
4. 種火 2024/7/4
5. 合気道の指導法 2024/7/16
「令和6年のおしらせ」に7月の稽古予定(再度変更有り) 稽古の記録 2010/8/15〜2024/7/24
*神氣館【 高槻市 天神町道場 】 Shinkikan aikido tenjinmachi-dojo
(公財)合気会公認道場 Takatsuki-city Osaka JAPAN
大阪府合気道連盟加盟道場
開祖植芝盛平の言葉と思いを動作する basic techniques from words and thoughts of the Founder, Morihei Ueshiba
不動の軸足に陰の魂氣:〝吾勝〟 非軸足と魂の比礼振り:〝正勝〟
〝この左、右の気結びがはじめ成就すれば、後は自由自在に出来るようになる〟:軸足交代
二つはこんで一と足すすむ・入り身一足と、体軸に与る両手の巡り:〝左右一つに勝速日、業の実を生む〟
〝正勝吾勝〟で剣素振り 合気の剣は〝勝速日〟
「天の浮橋」のタイトルに 3. 合気道は争わない、表と裏で気結びする 2024/5/20
4. 種火 2024/7/4
5. 合気道の指導法 2024/7/16
「令和6年のおしらせ」に7月の稽古予定(再度変更有り) 稽古の記録 2010/8/15〜2024/7/24

